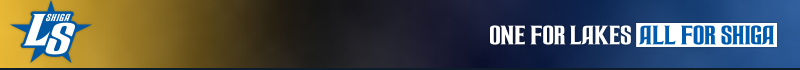B1残留を決めたレギュラーシーズン60試合を終えて
王者三河を破っての残留決定、今季初の6連勝でシーズンフィニッシュと、最高の形でシーズンを締めくくることができました。60試合の長いシーズン、おつかれさまでした。
――ありがとうございます。
チームはシーズンを通じて素晴らしい成長を遂げてくれました。
年明けは僅か6勝、3月下旬の交流戦が終わった時点でもリーグ最下位で、圧倒的に残留プレーオフや降格の最有力候補だったチームの奇跡のような躍進はとても美しい光景でした。
終盤は『FINISH STRONG』、力強くシーズンを終えようと、この言葉が魂の宿った言霊のように我々の意識を支配し、チームは力強く戦い抜き、我々はついにFINISH STRONGしました。
昨シーズンからの選手が横江・小林・ジュリアンの3人のみで、7月に集まったばかりの、それもbj・NBL・NBDL・ルーキーなどそれぞれが違うリーグから集まり、さらに並里が11月、クレイグが1月とプレーメーカーの2人が途中加入ということもあり、チーム作りに時間がかかってしまいました。
しかし、選手達は自分達を信じ、最初から最後までファイトし、まさに彼らが自分達自身の手で勝ち取ったB1残留です。
半年以上前、10月のこのブログで私は沖縄戦後に「彼らならより力強い勝者になれる」、京都戦後に「今年のチームは良い」と書いてありますが、やはり今も同じことを思っています。

5/3の大阪戦での終盤の逆転劇、また残留を決めた5/6は3Qに三河を12点に抑えて大きくリードを奪うなど、シーズン終盤のチームの勢いはめざましいものでした。
――我々は自力で残留プレーオフ圏内を抜け出せると信じていました。
例えば、4月9日の琉球戦を終え残り9試合となったところで田中が復帰できる状態になり、そこで田中は練習のハドルの時に「自力でのB1残留を諦めていない」とチームに話してくれました。
また、2位争いが加熱していた西地区で、終盤はどのチームにとってもレイクスとのゲームはポイントとなっており、4月は多くのゲームで「滋賀に負けたらプレーオフが無くなる」「滋賀に勝てばプレーオフが決まる」というシチュエーションが多く、プレッシャーがかかるヒリヒリとしたゲームが続きました。
その中でクレイグは「他のチームは関係ない。ただ1戦1戦、目の試合にファイトするだけ。その積み重ねだけだし自分達ならできる。プレッシャーなんて全く無いよ」と何度もチームに話してくれました。
他のチームの結果も先のことも気にせず、選手達はただ1戦1戦、ベストを尽くし勝利を目指しました。
振り返ると、前半戦でわずか6勝に留まったところから、チームは力強く巻き返してきました。特に終盤戦はゲーム中に崩れることが減り、逆転劇も数多く見られました。この粘り強さが、4月以降10勝3敗の快進撃の原動力になったと感じます。
――彼らの粘り強さは、シーズンを通じてどんな時も丁寧に取り組んできたことの賜物で、何度も経験してきたオフェンス・ディフェンス共に「この1本を」ということに彼らがギブアップせず戦い続けた結果です。
「粘り強さ」など、こういうことにショートカットは無いのです。
12月川崎戦や1月横浜戦、2月アルバルク戦や3月名古屋戦などは、終盤に驚異的な追い上げを見せ始めた試合で、その中には敗北も勝利もありましたが、選手達はゲーム終盤の追い上げや強さに自信を持ち始め、4Q開始時に少しのビハインドなら「これはオレ達のゲームだ」と思えるようになり、自分達の勝ち方を知り確立できるようになっていきました。
誰かがスターになることはなく、チームとして勝つ方法を見出すこと、並里・ジュリアン・クレイグの3人がバランスよくアタックできるスポットを探し、特に私としてはゲーム終盤にオープンの狩野や長谷川にボールが届いた時は「勝った」と思いました。
彼らは実際にかなり決めきってくれましたが、オープンの狩野と長谷川にボールが届くということは、チームがアンセルフィッシュにプレーしている、ボールが動いている、オフェンスが成功している、という証拠ですので「もしショットを外しても構わない、継続していれば勝てる」と思っていました。
ブースターの皆さんも、4Q終盤にオープンの狩野や長谷川にボールが届いた瞬間の興奮はたまらなかったでしょう。
シーズン序盤から中盤にかけては、長谷川の負傷、田中の離脱、メンバーの入れ替えなど、幾多の波がありました。そこから終盤にかけて盛り返してきた、このチーム力の向上をもたらした要因はどこにあったと感じますか。
――要因はいくつもあり、様々な要素が絡み合った結果だと思います。
当然、並里とクレイグの加入と彼らがチームにフィットし能力を発揮したことは大きな要因でしたし、田中の離脱後は役割と自身をよりマッチさせステップアップしてくれた菅原の働き、シーズンを通じて成長しアドバンテージを活かし相手の脅威をなってくれたサンバ、怪我からの復帰後はコンスタントにスコアし田中と共にディフェンスの要としても働いてくれた長谷川、難しい状況の中いつもどうにかしようと注意深く練習やゲーム、チームを見て常に準備をしていた横江のメンタリティがチームを救ったことなど、個人だけを挙げても沢山あります。
また、悪い時にその人間の本性が出ると言いますが、彼らはどんな辛い時でも我慢強く前を向いて丁寧に取り組み続けてくれました。
そういった努力が実を結んだことも間違いありません。
シーズン最後のブログですのでたまには私自身のことを書かせて頂ければ、今シーズンの私のチームへのアプローチとしては、今のラインナップはファイトする選手達が揃った為、私のエゴや威厳よりもいくつかの側面で選手達に主導権を持たせるよう心掛けました。
彼らの年齢やキャリアを考えた時に、選手に主導権を持たせることは危険と思われるかもしれませんが、今ここに到達する為には彼らが集団責任を理解することと成長することが必要不可欠でした。
タフな状況が訪れることが予想されるシーズンで、想像以上の厳しい場面に遭遇したときに崩れずに耐え抜く為に、ゲーム中に自分達の手でアジャストや修正しなければならない状況が多くなった場合に備え、ネガティブな感情に支配されずに常に解決に向けてフォーカスできるよう選手同士のコミュニケーションを重視しました。
また、若い彼らに責任を持ってプレーしてもらう為、これまでは私が何でも決めることが多かったですが、今シーズンは練習内容、ゲームプランや対戦相手へのディフェンスの方法もできる限り選手と相談して決めようとしました。
到達地点を考え、そこへの方法がいくつかある場合、同じ到達地点であれば私のエゴや威厳よりも選手達が成長できるプロセスを選択しようとしました。
また、タフなシーズンになることを考え、彼らの持つ特別な明るさは大切にするよう伝えていて、実際に彼らの明るさには私も救われました。
例年に比べるとチームを「コントロールする」というより正しい方向へ「ガイドする」と考え方で指揮をとり、過去2年私と一緒にやっていた横江と小林からしたら信じられない光景も沢山あったと思います。
終盤、4月に入る頃からはチームの骨格はできつつあったので、より一層ゲームにフォーカスできるように練習内容や練習時間などを大きく変え、削れるストレスはできる限り削ろうとしました。
結果的には選手達はできる範囲内で心身共に良いコンディションでゲームに臨むことができたと思っていますが、
これらはトレーナーなどスタッフ陣、伊藤・三木・上田達がいなければ成り立たず、スタッフ陣が選手のコンディションを上げる為に尽力しくれたお陰です。
最後に、最終節のアウェー刈谷において実況アナウンサーが驚くほど大きなレイクスへの声援が響くなど、今季はブースターの後押しがこれまで以上に感じられました。実際に、ホームゲームの来場者数は昨季比44%増の64127人、1試合平均も同30%増の2,138名と、いずれも過去最多に上りました。シーズンを共に戦い、共にB1残留を掴み取ったブースターの皆さんにメッセージをお願いします。
――我々はいくつもの幸運に助けられシーズンを力強く終えることができましたが、そのうちの大きな1つはレイクスブースターの皆さんがレイクスのブースターであったことです。
シーズンを通じてどんなに苦しい時でも皆さんは大きなご声援を届けてくれました。
また、終盤の躍進も我々にとって幸運だったことは、4月に入ってからホームゲームが多かったこと、又は京都や大阪などレイクスブースターの皆さんが来やすい比較的近い場所でゲームができたことです。
スポナビなどの音声が割れてしまう程の大歓声が無ければ我々はもっと大変なシーズンでしたし、特に4Qのチームとブースターの一体感はレイクスのホームゲームでしか味わえないスペシャルなものでした。
そこにはレイクス・チアの皆さんの力があり、彼女達のお陰で会場のボルテージが上がり、一体感が生まれたのだと思います。
チームは序盤から沢山のゲームに負けてしまいましたが、レイクスブースターはB1でもスペシャルだと証明されたシーズンでもありました。
リーグにはチームカラーが青のチームはいくつもありますが、『スペシャル・ブルー』のレイクスブースターの皆さんとレイクス・チアを心から誇りに思っています。
ご協力・ご支援頂きましたスポンサー・パートナーの皆様、関係者各位、ブースターの皆様、ボランティアスタッフの皆様、レイクスを観て頂いた全ての皆様に心から御礼申し上げます。
今シーズンありがとうございました。
――ありがとうございます。
チームはシーズンを通じて素晴らしい成長を遂げてくれました。
年明けは僅か6勝、3月下旬の交流戦が終わった時点でもリーグ最下位で、圧倒的に残留プレーオフや降格の最有力候補だったチームの奇跡のような躍進はとても美しい光景でした。
終盤は『FINISH STRONG』、力強くシーズンを終えようと、この言葉が魂の宿った言霊のように我々の意識を支配し、チームは力強く戦い抜き、我々はついにFINISH STRONGしました。
昨シーズンからの選手が横江・小林・ジュリアンの3人のみで、7月に集まったばかりの、それもbj・NBL・NBDL・ルーキーなどそれぞれが違うリーグから集まり、さらに並里が11月、クレイグが1月とプレーメーカーの2人が途中加入ということもあり、チーム作りに時間がかかってしまいました。
しかし、選手達は自分達を信じ、最初から最後までファイトし、まさに彼らが自分達自身の手で勝ち取ったB1残留です。
半年以上前、10月のこのブログで私は沖縄戦後に「彼らならより力強い勝者になれる」、京都戦後に「今年のチームは良い」と書いてありますが、やはり今も同じことを思っています。

5/3の大阪戦での終盤の逆転劇、また残留を決めた5/6は3Qに三河を12点に抑えて大きくリードを奪うなど、シーズン終盤のチームの勢いはめざましいものでした。
――我々は自力で残留プレーオフ圏内を抜け出せると信じていました。
例えば、4月9日の琉球戦を終え残り9試合となったところで田中が復帰できる状態になり、そこで田中は練習のハドルの時に「自力でのB1残留を諦めていない」とチームに話してくれました。
また、2位争いが加熱していた西地区で、終盤はどのチームにとってもレイクスとのゲームはポイントとなっており、4月は多くのゲームで「滋賀に負けたらプレーオフが無くなる」「滋賀に勝てばプレーオフが決まる」というシチュエーションが多く、プレッシャーがかかるヒリヒリとしたゲームが続きました。
その中でクレイグは「他のチームは関係ない。ただ1戦1戦、目の試合にファイトするだけ。その積み重ねだけだし自分達ならできる。プレッシャーなんて全く無いよ」と何度もチームに話してくれました。
他のチームの結果も先のことも気にせず、選手達はただ1戦1戦、ベストを尽くし勝利を目指しました。
振り返ると、前半戦でわずか6勝に留まったところから、チームは力強く巻き返してきました。特に終盤戦はゲーム中に崩れることが減り、逆転劇も数多く見られました。この粘り強さが、4月以降10勝3敗の快進撃の原動力になったと感じます。
――彼らの粘り強さは、シーズンを通じてどんな時も丁寧に取り組んできたことの賜物で、何度も経験してきたオフェンス・ディフェンス共に「この1本を」ということに彼らがギブアップせず戦い続けた結果です。
「粘り強さ」など、こういうことにショートカットは無いのです。
12月川崎戦や1月横浜戦、2月アルバルク戦や3月名古屋戦などは、終盤に驚異的な追い上げを見せ始めた試合で、その中には敗北も勝利もありましたが、選手達はゲーム終盤の追い上げや強さに自信を持ち始め、4Q開始時に少しのビハインドなら「これはオレ達のゲームだ」と思えるようになり、自分達の勝ち方を知り確立できるようになっていきました。
誰かがスターになることはなく、チームとして勝つ方法を見出すこと、並里・ジュリアン・クレイグの3人がバランスよくアタックできるスポットを探し、特に私としてはゲーム終盤にオープンの狩野や長谷川にボールが届いた時は「勝った」と思いました。
彼らは実際にかなり決めきってくれましたが、オープンの狩野と長谷川にボールが届くということは、チームがアンセルフィッシュにプレーしている、ボールが動いている、オフェンスが成功している、という証拠ですので「もしショットを外しても構わない、継続していれば勝てる」と思っていました。
ブースターの皆さんも、4Q終盤にオープンの狩野や長谷川にボールが届いた瞬間の興奮はたまらなかったでしょう。
シーズン序盤から中盤にかけては、長谷川の負傷、田中の離脱、メンバーの入れ替えなど、幾多の波がありました。そこから終盤にかけて盛り返してきた、このチーム力の向上をもたらした要因はどこにあったと感じますか。
――要因はいくつもあり、様々な要素が絡み合った結果だと思います。
当然、並里とクレイグの加入と彼らがチームにフィットし能力を発揮したことは大きな要因でしたし、田中の離脱後は役割と自身をよりマッチさせステップアップしてくれた菅原の働き、シーズンを通じて成長しアドバンテージを活かし相手の脅威をなってくれたサンバ、怪我からの復帰後はコンスタントにスコアし田中と共にディフェンスの要としても働いてくれた長谷川、難しい状況の中いつもどうにかしようと注意深く練習やゲーム、チームを見て常に準備をしていた横江のメンタリティがチームを救ったことなど、個人だけを挙げても沢山あります。
また、悪い時にその人間の本性が出ると言いますが、彼らはどんな辛い時でも我慢強く前を向いて丁寧に取り組み続けてくれました。
そういった努力が実を結んだことも間違いありません。
シーズン最後のブログですのでたまには私自身のことを書かせて頂ければ、今シーズンの私のチームへのアプローチとしては、今のラインナップはファイトする選手達が揃った為、私のエゴや威厳よりもいくつかの側面で選手達に主導権を持たせるよう心掛けました。
彼らの年齢やキャリアを考えた時に、選手に主導権を持たせることは危険と思われるかもしれませんが、今ここに到達する為には彼らが集団責任を理解することと成長することが必要不可欠でした。
タフな状況が訪れることが予想されるシーズンで、想像以上の厳しい場面に遭遇したときに崩れずに耐え抜く為に、ゲーム中に自分達の手でアジャストや修正しなければならない状況が多くなった場合に備え、ネガティブな感情に支配されずに常に解決に向けてフォーカスできるよう選手同士のコミュニケーションを重視しました。
また、若い彼らに責任を持ってプレーしてもらう為、これまでは私が何でも決めることが多かったですが、今シーズンは練習内容、ゲームプランや対戦相手へのディフェンスの方法もできる限り選手と相談して決めようとしました。
到達地点を考え、そこへの方法がいくつかある場合、同じ到達地点であれば私のエゴや威厳よりも選手達が成長できるプロセスを選択しようとしました。
また、タフなシーズンになることを考え、彼らの持つ特別な明るさは大切にするよう伝えていて、実際に彼らの明るさには私も救われました。
例年に比べるとチームを「コントロールする」というより正しい方向へ「ガイドする」と考え方で指揮をとり、過去2年私と一緒にやっていた横江と小林からしたら信じられない光景も沢山あったと思います。
終盤、4月に入る頃からはチームの骨格はできつつあったので、より一層ゲームにフォーカスできるように練習内容や練習時間などを大きく変え、削れるストレスはできる限り削ろうとしました。
結果的には選手達はできる範囲内で心身共に良いコンディションでゲームに臨むことができたと思っていますが、
これらはトレーナーなどスタッフ陣、伊藤・三木・上田達がいなければ成り立たず、スタッフ陣が選手のコンディションを上げる為に尽力しくれたお陰です。
最後に、最終節のアウェー刈谷において実況アナウンサーが驚くほど大きなレイクスへの声援が響くなど、今季はブースターの後押しがこれまで以上に感じられました。実際に、ホームゲームの来場者数は昨季比44%増の64127人、1試合平均も同30%増の2,138名と、いずれも過去最多に上りました。シーズンを共に戦い、共にB1残留を掴み取ったブースターの皆さんにメッセージをお願いします。
――我々はいくつもの幸運に助けられシーズンを力強く終えることができましたが、そのうちの大きな1つはレイクスブースターの皆さんがレイクスのブースターであったことです。
シーズンを通じてどんなに苦しい時でも皆さんは大きなご声援を届けてくれました。
また、終盤の躍進も我々にとって幸運だったことは、4月に入ってからホームゲームが多かったこと、又は京都や大阪などレイクスブースターの皆さんが来やすい比較的近い場所でゲームができたことです。
スポナビなどの音声が割れてしまう程の大歓声が無ければ我々はもっと大変なシーズンでしたし、特に4Qのチームとブースターの一体感はレイクスのホームゲームでしか味わえないスペシャルなものでした。
そこにはレイクス・チアの皆さんの力があり、彼女達のお陰で会場のボルテージが上がり、一体感が生まれたのだと思います。
チームは序盤から沢山のゲームに負けてしまいましたが、レイクスブースターはB1でもスペシャルだと証明されたシーズンでもありました。
リーグにはチームカラーが青のチームはいくつもありますが、『スペシャル・ブルー』のレイクスブースターの皆さんとレイクス・チアを心から誇りに思っています。
ご協力・ご支援頂きましたスポンサー・パートナーの皆様、関係者各位、ブースターの皆様、ボランティアスタッフの皆様、レイクスを観て頂いた全ての皆様に心から御礼申し上げます。
今シーズンありがとうございました。
ホーム名古屋戦、アウェー大阪戦レビュー
アウェー大阪の大観衆に負けず、勝利をつかんで残留へのマジック1で最終節に臨むレイクス。今回の「遠山の地声」は、30日(日)のホーム名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦、3日(水・祝)のアウェー大阪エヴェッサ戦終了後の記者会見での遠山HCのコメントを中心に、お届けします。

【名古屋戦後】=============
二日連続の延長というハードなゲームで、名古屋のハードなディフェンスに苦しみましたが、選手たちがよく我慢して、声を掛け合って、互いを信じあってくれました。
2Qに横江がオフェンス面でいいゲームコントロールをしてくれました。ベンチからもいつもゲームの流れをよく見ている証だと思います。横江の好きなスポットまでボールが回るのは、チームがうまくいっている証拠かなと思います。
(Q.ブラッキンズ選手のシーズンハイ36点について)
張本選手がついている中、難しいシュートをよく決めたな、という場面が多かったですが、もともとのスキルからすると、あれだけのシュートを決めるスキルは持っている選手です。
4Q終了間際にビッグショットで追いつかれてのオーバータイムで、雰囲気が悪かったので、リバウンドで負けないように、そしてオフェンスで迷いが生じないように、コールを確認して臨みました。シーズン序盤は接戦で勝ちきれないケースもありましたが、ここにきて自分たちのいい形を自分たちでわかってきているのが大きいと思います。
【大阪戦後】=============
前半はうまくいかないことが多くて、苦しかったですが、ゲームの中で修正しようとコミュニケーションをとって、勝利を勝ち取ってくれました。
(Q.ハーフタイムでの指示は)
相手に多く取られていたリバウンドの修正と、トランジションディフェンスを戻らなかったりという、少しだらしないところがあったので、しっかりしようと確認しました。ただ、よく我慢できてプレーできていて、1Qでオンザコートがずれてリードされましたが、予定通り2Qで追い上げてペースできているので、そのままでいこうと伝えました。
(Q.4Qに入る前での指示は)
自分たちのボールムーブメントを実行するように伝えました。
(Q.今日はサンバのアドバンテージがなかなか生かせませんでした)
大阪が対策練ってきたこともあり、サンバまでボールが届いていなかったので、まずはそこまでボールを届けるように伝えました。
また、根来選手の3Pへのディフェンスにミスがあったので、アウェーの大歓声で指示の声も届かなかったので、樋口に代えて、ディフェンスから修正しました。

【名古屋戦後】=============
二日連続の延長というハードなゲームで、名古屋のハードなディフェンスに苦しみましたが、選手たちがよく我慢して、声を掛け合って、互いを信じあってくれました。
2Qに横江がオフェンス面でいいゲームコントロールをしてくれました。ベンチからもいつもゲームの流れをよく見ている証だと思います。横江の好きなスポットまでボールが回るのは、チームがうまくいっている証拠かなと思います。
(Q.ブラッキンズ選手のシーズンハイ36点について)
張本選手がついている中、難しいシュートをよく決めたな、という場面が多かったですが、もともとのスキルからすると、あれだけのシュートを決めるスキルは持っている選手です。
4Q終了間際にビッグショットで追いつかれてのオーバータイムで、雰囲気が悪かったので、リバウンドで負けないように、そしてオフェンスで迷いが生じないように、コールを確認して臨みました。シーズン序盤は接戦で勝ちきれないケースもありましたが、ここにきて自分たちのいい形を自分たちでわかってきているのが大きいと思います。
【大阪戦後】=============
前半はうまくいかないことが多くて、苦しかったですが、ゲームの中で修正しようとコミュニケーションをとって、勝利を勝ち取ってくれました。
(Q.ハーフタイムでの指示は)
相手に多く取られていたリバウンドの修正と、トランジションディフェンスを戻らなかったりという、少しだらしないところがあったので、しっかりしようと確認しました。ただ、よく我慢できてプレーできていて、1Qでオンザコートがずれてリードされましたが、予定通り2Qで追い上げてペースできているので、そのままでいこうと伝えました。
(Q.4Qに入る前での指示は)
自分たちのボールムーブメントを実行するように伝えました。
(Q.今日はサンバのアドバンテージがなかなか生かせませんでした)
大阪が対策練ってきたこともあり、サンバまでボールが届いていなかったので、まずはそこまでボールを届けるように伝えました。
また、根来選手の3Pへのディフェンスにミスがあったので、アウェーの大歓声で指示の声も届かなかったので、樋口に代えて、ディフェンスから修正しました。